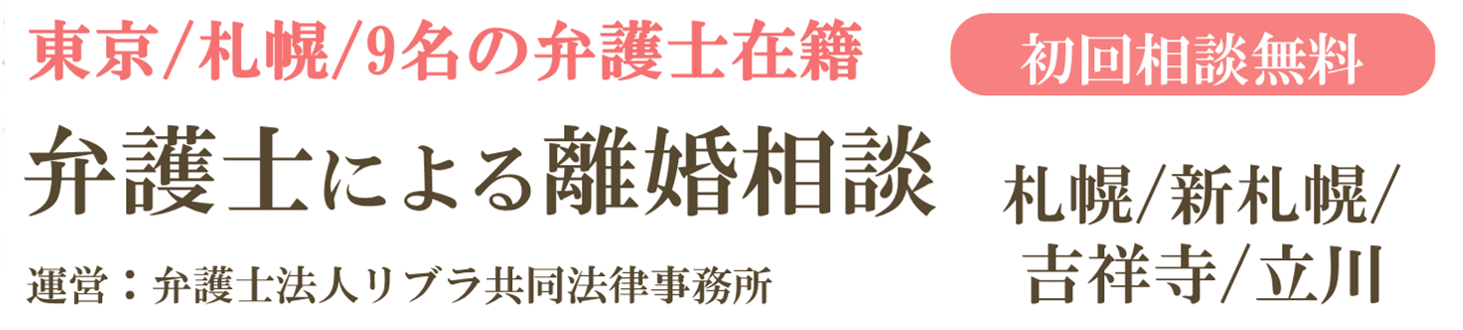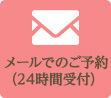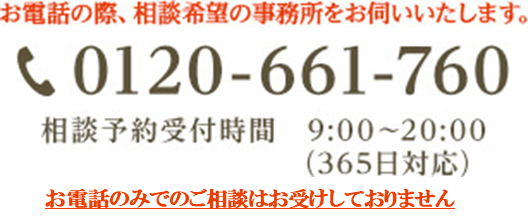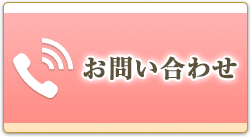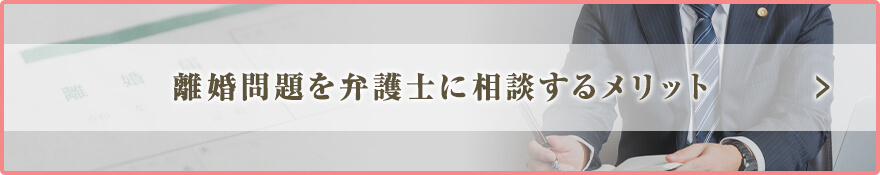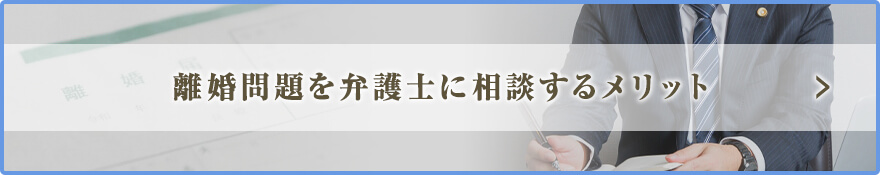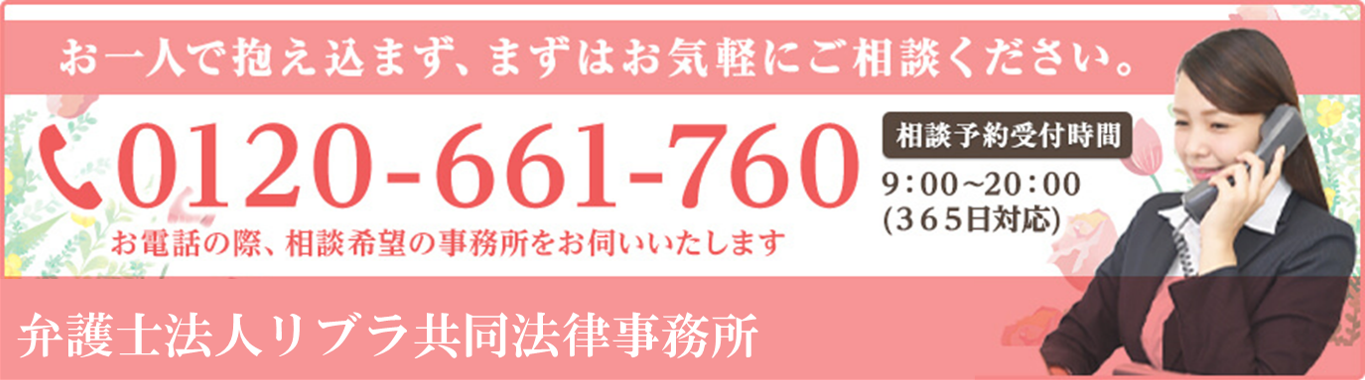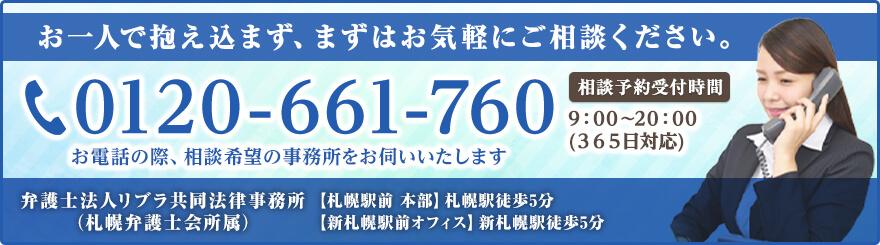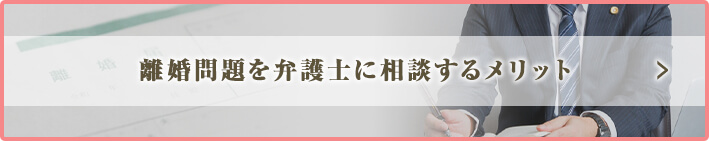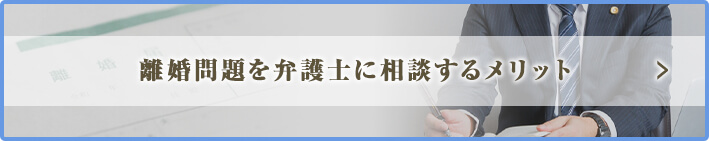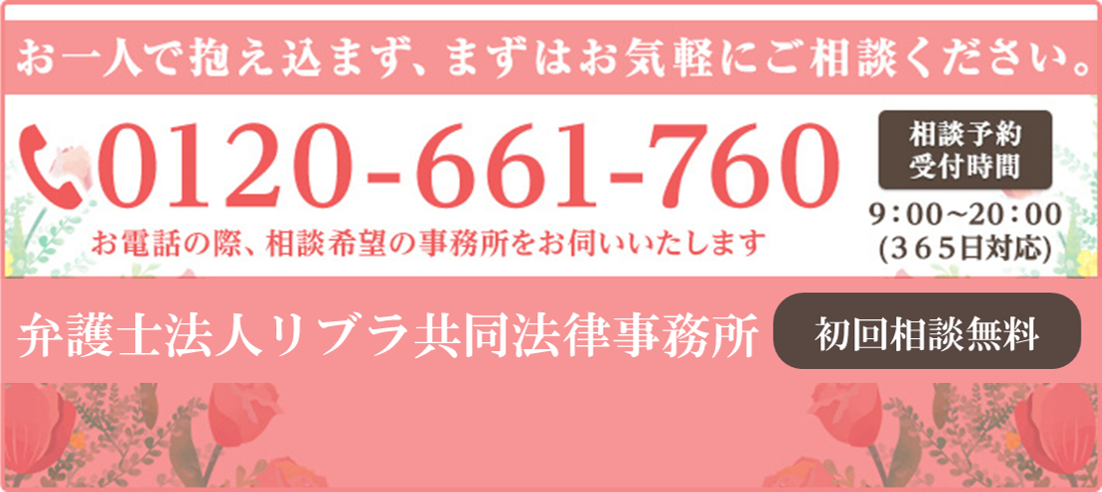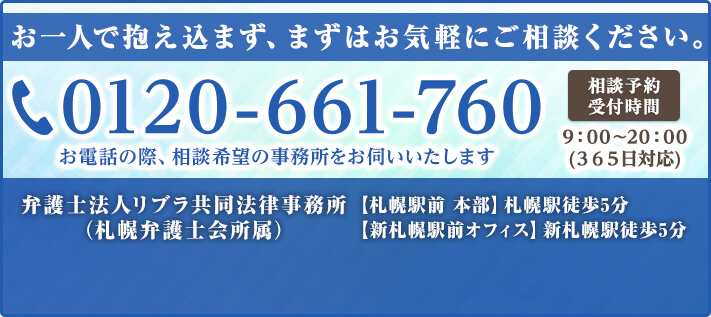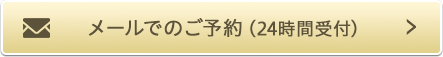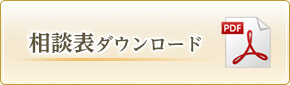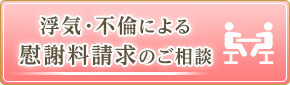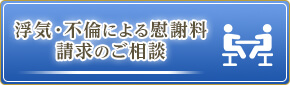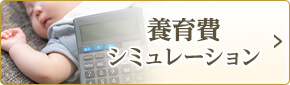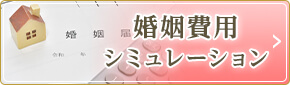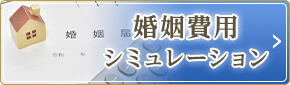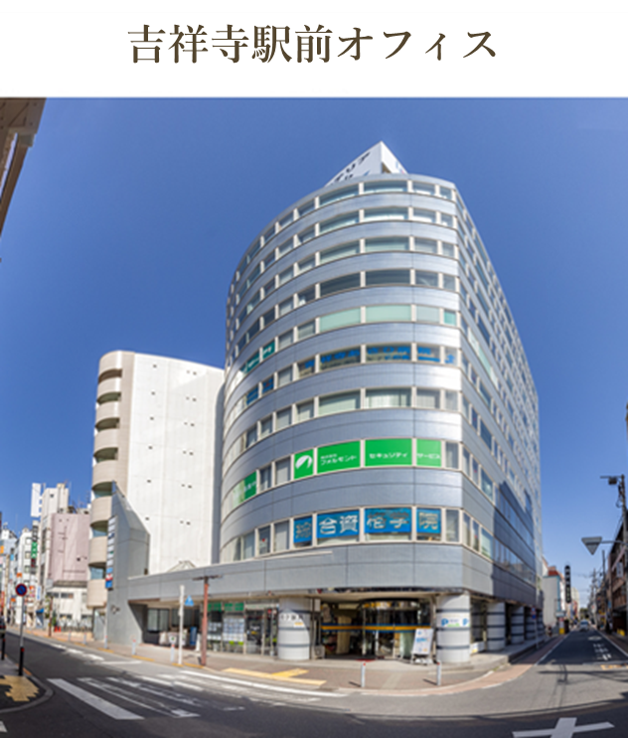アンダーローン不動産(持ち家)の財産分与の方法とは?不動産の財産分与に詳しい弁護士が解説
目次
持ち家をもつご夫婦が離婚を考えるとき、持ち家の扱いは最も揉めやすい争点の一つです。
特に「アンダーローン」、すなわち住宅ローン残債を住宅の資産価値が上回る状態では、その持ち家の分け方次第で離婚後の生活設計にも影響が出ます。
本記事では、東京23区内など地価が高いエリアを想定しつつ、アンダーローンの持ち家が財産分与にどう作用するかという点や、分与の具体的な方法や注意点について弁護士法人リブラ共同法律事務所の弁護士が整理しています。
東京23区内における不動産価格の高騰
近年、東京23区内の不動産価格は継続的に上昇しています。特に2020年代以降、再開発や低金利政策、外国人投資家の参入などの影響も受け、都心部を中心に不動産価格は高騰しています。
こうした状況の中で、「離婚時に持ち家をどう扱うか」という問題は、以前にも増して複雑になっています。購入当初は3000万円台だった物件が、現在では5000万円以上の価値を持つことも珍しくありません。
アンダーローンとは
「アンダーローン」とは、不動産の時価が住宅ローン残高を上回っている状態をいいます。
たとえば、持ち家の現在の市場価値が4000万円で、ローンの残りが2500万円であれば、差額の1500万円がプラスの財産になっている「アンダーローン」の状態といえます。
この反対に、時価よりローン残高の方が多い場合は「オーバーローン」と呼ばれます。
離婚時の財産分与では、持ち家がこの「アンダーローン」か「オーバーローン」のいずれになっているかによって扱われ方が大きく変わります。
つまり、アンダーローンの状態であれば、家を売却してローンを完済した後に残った利益を夫婦でどう分け合うかを協議することになりますが、オーバーローンの場合は売却してもローンが残り、財産分与どころか「負債をどう分担するか」が争点になるわけです。
アンダーローンの持ち家はプラスの大きな資産になりうる反面、その分配方法を巡ってトラブルに発展しやすい特徴があります。特に、住宅ローンの名義が一方の配偶者のみで、実際の返済を夫婦が協力して行っていた場合、「どこまで共有財産といえるのか」を正しく理解する必要があります。
離婚時のアンダーローンの不動産(持ち家)が財産分与に与える影響
法律上、婚姻中に夫婦の協力によって形成された財産(共有財産)を離婚時に分け合う権利(財産分与請求権)が認められています(民法第768条)。
持ち家についても、結婚後に夫婦で同居し夫婦の家計で住宅ローンを支払ってきたものについては実際の名義にかかわらず共有財産として財産分与の対象になります。
ただし、財産分与の際には単に不動産価格を半分にするのではなく、ローン残高を差し引いた純資産額をもとに計算します。
例えば、時価4000万円、ローン残高2000万円の持ち家であれば、財産分与の対象となる純資産は4000-2000=2000万円であり、その半分である1000万円が夫妻それぞれの取り分の目安になります。
また、評価方法にも注意が必要です。不動産会社の査定額はあくまで「売却想定価格」であり、実際に売れる価格とは異なることがあります。思わぬ損を防ぐためには、必要に応じて複数の業者に査定を依頼し、客観的な時価を把握することが大切です。
アンダーローンの不動産(持ち家)を財産分与する2つの方法
アンダーローンの持ち家の財産分与には、大きく分けて次の2つの方法があります。
●夫婦のいずれか一方が住み続ける方法
夫婦の一方が持ち家を取得し住み続け、もう一方に相応の代償金を支払う方法です。
たとえば、家の純資産が2000万円のときに、夫が家に住み続ける代わりに、妻に1000万円を支払う形をとるものです。
ただし、住宅ローンの名義変更ができない場合、ローン契約者が引き続き残ったローンの返済義務を負う点には注意が必要です。金融機関が名義変更を認めるのは、取得する側に十分な返済能力がある場合に限られます。
●売却して現金を分ける方法
不動産を売却してローンを完済し、残ったお金を分ける方法です。公平で分かりやすい方法ですが、売却時期や価格の決定をめぐって対立するケースもあります。例えば、購入から離婚までの期間が短いケースだと住宅ローンの返済が進んでおらず、完済しても大きな利益が残らない場合には財産分与できる額が小さくなることもありますし、双方が納得できる金額で売却するまで時間がかかることも珍しくありません。
また、売却益が発生した場合には譲渡所得税が課される可能性もあるため、税務面の事前確認も欠かせません。持ち家を売却する方法で財産分与を行う際は、売却によって得た利益の扱い、譲渡税の負担割合、引っ越し費用の分担なども取り決めて書面化しておくことで、後のトラブルを防ぐことが推奨されます。
持ち家の売却によって慰謝料を支払うことはできる?
離婚原因が不貞行為や暴力にあるなど、夫婦のいずれかの帰責性が高い場合の離婚では、慰謝料の支払いが問題となることがあります。
この際、アンダーローンの持ち家の売却益から慰謝料を支払うことは可能ですが、財産分与として渡す財産と慰謝料として支払う金銭は性質が異なるということに注意しなければなりません。財産分与は「婚姻中の協力によって築いた財産を公平に分ける」ものであるのに対し、慰謝料は「精神的苦痛に対する損害賠償」と明確に区別されるものですので、例えば「持ち家の売却益2000万円を夫婦で案分し、夫が妻に慰謝料300万円を支払う」と取り決めたケースでは、妻が売却益から分与を受ける分(2000万÷2=1000万円)を侵害しないようにする必要があり、夫が受け取る1000万円から慰謝料300万円を支払うことになります。
離婚時に不動産(持ち家)を財産分与する際の注意点
離婚時に不動産(持ち家)を財産分与する場合には、単純に「どちらかが住み続ける」「売る」といった判断だけでは済まないことが多くあります。不動産は高額であり、ローンや税金、名義、評価方法など複数の問題が絡むため、慎重な対応が必要です。
まず注意すべきは住宅ローンの名義です。住宅ローンは契約者本人に返済義務がありますが、例え夫名義でローンを組んでいた家に離婚後に妻がその家に住み続ける場合でも、金融機関が審査を経て債務者の名義変更を認めないことがあります。こうしたケースでは離婚後も夫が返済義務を負い続ける形となり、トラブルの原因になることがあります。
また、登記名義の変更にも費用と手続が必要です。財産分与により一方の名義に変更する場合は不動産登記法に定められた登記変更手続が必要で、手続の際には登録免許税などの費用も発生します。加えて、固定資産税や都市計画税などの税金負担の分担も明確にしておかないと、離婚後に思わぬ支払義務が残るケースもあります。
さらに、不動産の評価方法にも注意が必要です。不動産会社の査定額、固定資産税評価額、路線価など、評価の基準は複数存在します。どの基準で評価するかによって財産分与額が変わるため、合意前に正確な査定を行うことが大切です。
これらの点を曖昧にしたまま離婚協議書を作成してしまうと、後から「こんなはずではなかった」と紛争が再燃することも少なくありません。不動産の財産分与では、法的・税務的な知識をもつ弁護士の関与がトラブル防止に大きく役立ちます。
弁護士に相談するメリット:持ち家の財産分与を適切に取り決めるために
現金や預貯金のように単純に分けることのできない不動産(持ち家)を含む財産分与は、大きな金額が動くだけではなく複雑な問題を伴います。弁護士に相談することで、財産調査から評価、分与方法の選択、協議書の作成まで一貫したサポートを受けることができます。
特にローンが残った持ち家は単なる資産ではなく債務(マイナスの財産)の側面もあり、どちらかが住み続けるにしても売却するにしても法的な整理や金融機関との調整が必要になるため、専門知識が不可欠です。弁護士は、依頼者の利益を最大限に守るために交渉・書面作成を行い、公平で納得のいく解決を導きます。
離婚問題における弁護士の役割
弁護士は、依頼者の立場に立って相手方との交渉を代理し、感情的な対立を避けながらスムーズに話を進めることができます。持ち家の財産分与が争点になるケースでは法律はもちろん、関連する税務・不動産実務の知識も必要なため、離婚案件に詳しい弁護士の関与によって結果が大きく変わることもあります。
(弁護士によるサポートの例)
- 不動産の評価・ローン残債の整理
不動産会社や金融機関と連携し、時価とローン残高を把握したうえで、公平な分与額を算定します。 - 適正な合意書の作成
離婚協議書や財産分与契約書を法的に有効な形で作成し、後の紛争を防止します。 - 調停・訴訟での代理交渉
話し合いでまとまらない場合、家庭裁判所での調停や訴訟においても弁護士が代理人として主張・立証を行います。 - 税務・登記のアドバイス
不動産を分与する際の譲渡所得税や登録免許税の発生有無を確認し、必要に応じて専門家と連携します。
不動産が共有名義のケースや、自宅を売却して慰謝料の精算を行うケースなど、さらに複雑な事情が絡むこともあります。感情的な衝突を避けつつ、冷静に最善の結果を導くためにも、専門家に相談することをおすすめいたします。
離婚問題は弁護士法人リブラ共同法律事務所にご相談ください
当事務所では、離婚に伴う持ち家の財産分与についてもこれまで多数のご相談をお受けしてまいりました。住宅ローンの名義変更、持ち家の売却、残債の分担、名義人のトラブルなど、いずれの段階でもお気軽にご相談ください。
初回のご相談は無料で承っており、遠方にお住まいである等のご事情によってはオンライン相談にも対応しております。経験豊富な弁護士が、あなたの状況を丁寧に伺い、最適な解決方法をご提案します。
離婚後の生活を安心してスタートするためには、法的リスクを見逃さないことが大切です。持ち家をめぐる財産分与に不安を感じたときは、迷わず弁護士にご相談ください。将来のトラブルを防ぎ、納得のいく離婚を実現する第一歩になります。
監修者

- 弁護士法人リブラ共同法律事務所は離婚事件を中心に取り扱い、東京・札幌を中心に全国の皆様から多数の相談、依頼をいただいております。離婚についてお悩みのことがございましたら当事務所までお問い合わせください。
最新の投稿
- 2026.01.12離婚時のマンション(不動産)の財産分与について弁護士が解説
- 2025.12.11看護師の離婚問題について弁護士が解説
- 2025.10.15アンダーローン不動産(持ち家)の財産分与の方法とは?不動産の財産分与に詳しい弁護士が解説
- 2025.10.1570代女性の離婚問題
こちらもご覧ください
| ●弁護士紹介 | ●解決事例 | ●お客様の声 | ●弁護士費用 | ●5つの強み |