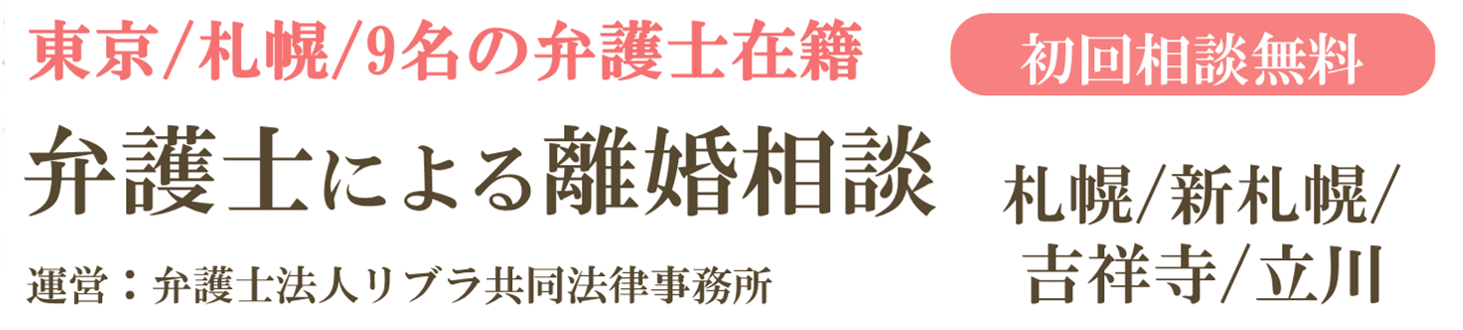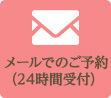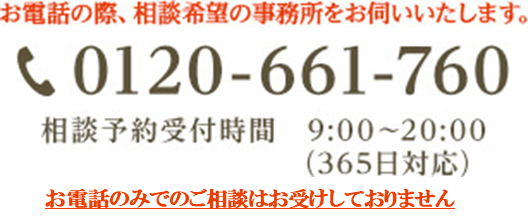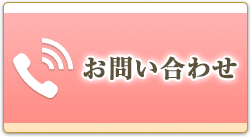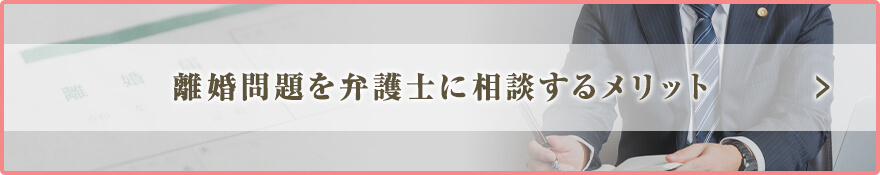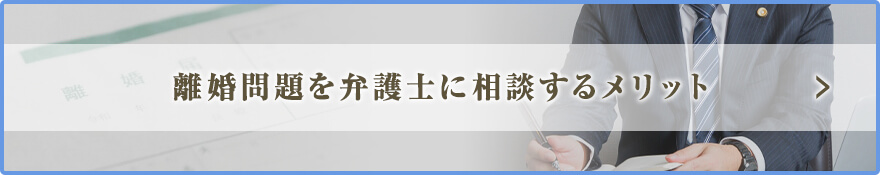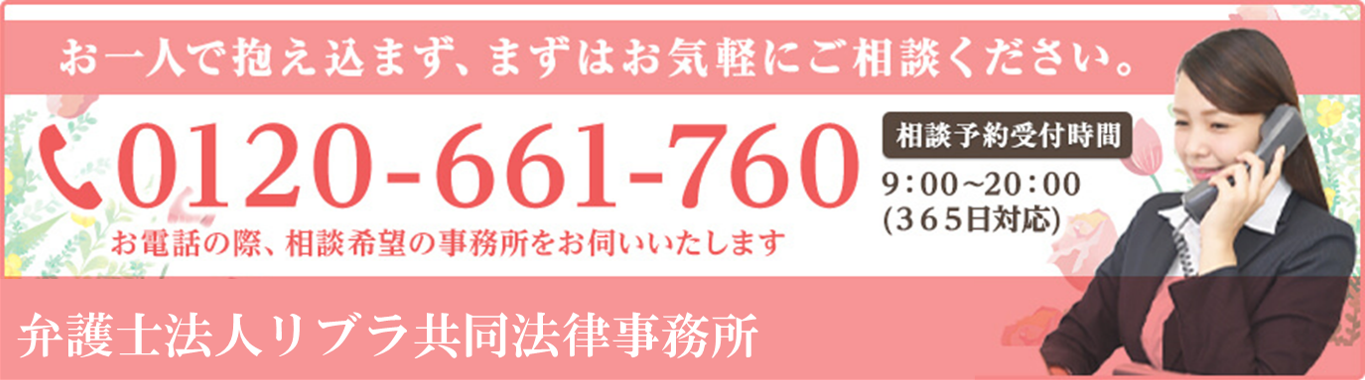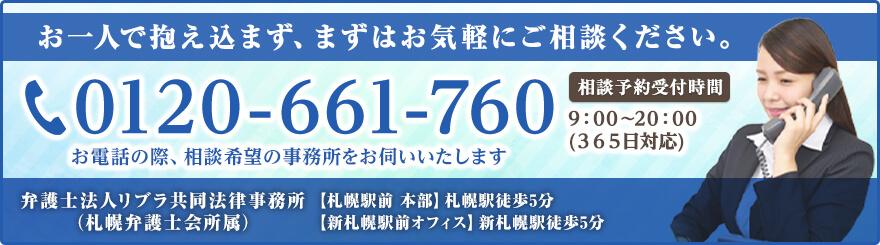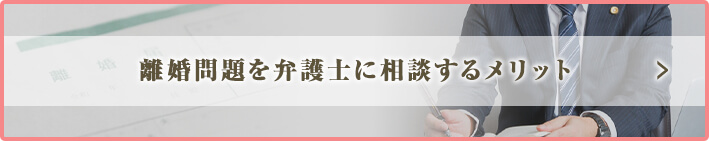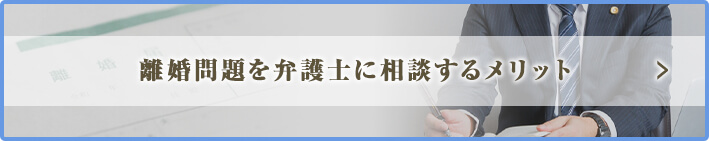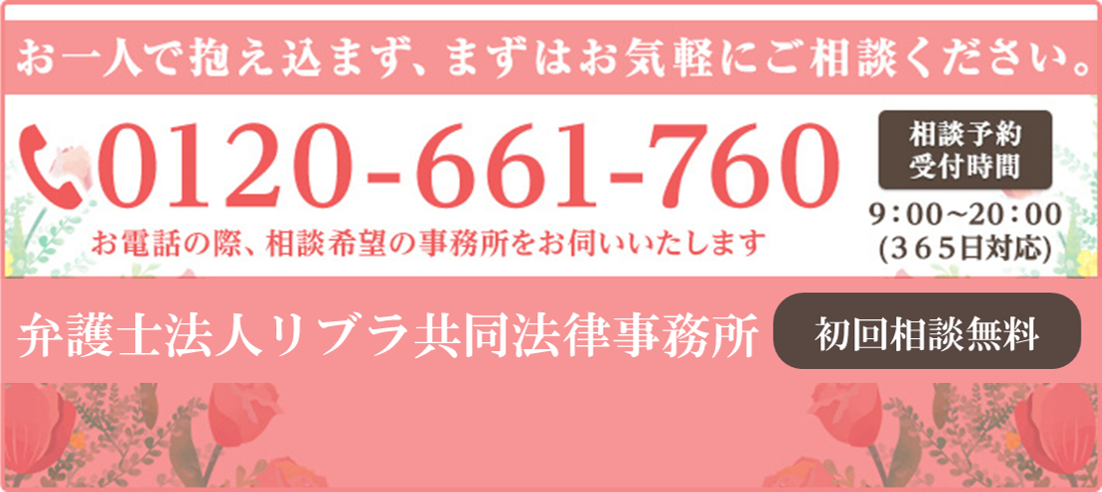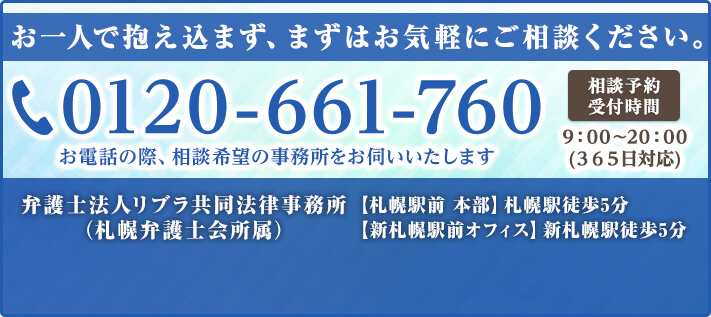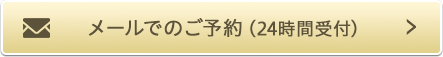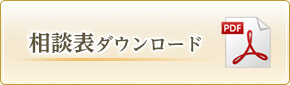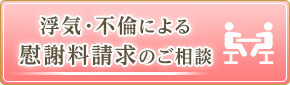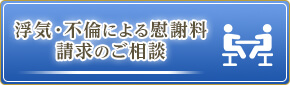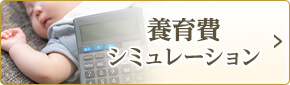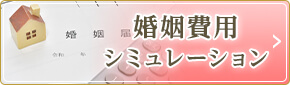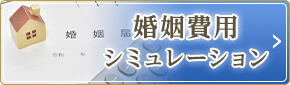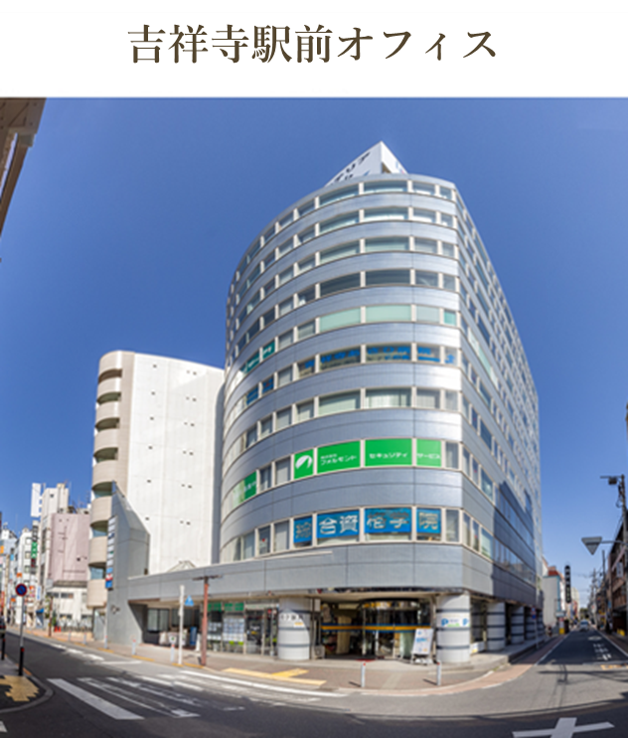医師・医者の妻の離婚問題を弁護士が解説~医師・医者の財産分与の方法とは~
目次
医師・医者の家庭は経済的には恵まれていることが多い一方で、長時間労働・強い責任・人間関係のプレッシャーなどから、夫婦関係がすれ違ってしまうことも少なくありません。
また医師と離婚、あるいは医師同士で離婚する際は、子どもの親権や養育費のように、相手がサラリーマンや公務員である場合と共通する部分も多くある一方で、①財産分与、②婚姻費用・養育費、③医療法人との関係、という点で特有の問題が生じることがあります。
こちらでは、医師特有の離婚原因や、医師との離婚の際に問題となりやすい上記3点について、離婚問題に注力している弁護士が説明いたします。
医師・医者特有の離婚原因
院内での不倫
医師の離婚原因としてよく見られるのが、「職場不倫(院内不倫)」です。医療の現場では医師・看護師・薬剤師などが長時間一緒に勤務することが多く、夜勤や緊急対応などを通じて親密な関係に発展してしまうケースがあります。
激務がもたらすストレス
医師の仕事には、常に命と向き合う緊張感や長時間労働が伴います。外科系の医師であれば、深夜や休日の緊急手術もあり、家庭生活に割ける時間が減ってしまいがちです。その結果、夫婦間の会話が少なくなり、すれ違いが生じることがあります。
また勤務医が転勤を繰り返す場合や、開業医が医師としての業務以外に経営面で忙殺される場合も同様に、夫婦の精神的な距離が広がる原因となりえます。
家事や育児への関わりが薄い・無関心
特に子どもが小さい時期には「妻が育児・家事を一手に担い、夫が家庭に関心を示さない」という状況が離婚原因に発展するケースがよく見られますが、特に医師は仕事に追われることが多く、「自分が家計を支えている」という意識から家庭内の不平等を感じにくい傾向にあります。この状況を医師の妻からみると、「経済的な安定」だけでは満たされず、「家庭を顧みない」「会話がない」ことから精神的な孤立を感じてしまうことにつながります。
財産分与について
(1)財産分与の対象
医師の方は、一般の世帯以上に所有する財産の種類や金額が多いため、財産分与の対象とする財産の内容を正確に把握し、また適切に評価にすることが大切です。
財産分与の対象となる財産としては、不動産、預貯金、保険、自動車が典型的なものとして挙げられると思いますが、その他にも、退職金や動産、有価証券も財産分与の対象となりえます。
そこで、双方が所有している
・高価な時計
・宝石等の貴金属類
・経営する医療法人への出資金
・ゴルフ会員権
の有無について確認するほか、相手の退職金、医療法人の理事であれば退職時に退職金として支給される保険の有無について把握しなければなりません。
以上のものはあくまで一例であり、医師の方との離婚する際の財産分与では、対象財産の内容・評価については留意すべき点が多くあります。
(2)財産分与の割合
財産分与の割合は、原則として夫婦で2分の1ずつ(50:50)です。これを実務上は「2分の1ルール」と呼んでいます。
しかし、夫婦の一方の特殊な能力・技能によって高額の資産形成がなされた場合には、2分の1ルールが適用されないことがあります。
財産分与は、夫婦が婚姻期間中に協力して形成・維持してきた財産を離婚にあたって清算するものですので、分与割合は共同財産に対する寄与の程度等の一切の事情を考慮して公平の観点から決せられることがその理由です。
医師である夫との離婚のケースでは、夫の才覚により一般的な家庭よりも多額の財産が形成できたとして財産分与の割合が大きな争点となることが多いです。
この場合、形成された財産が高額とはいえないこと、夫に2分の1ルールを修正する程の特段の事情が認められないこと、妻の財産形成・維持への寄与が認められることなどを詳細に主張して、2分の1ルールの修正が認められないと反論する必要がございます。
(3)個人開業医の財産分与
個人でクリニックや診療所を経営している開業医の離婚では、建物や土地、医療機器などの「事業用資産」も、婚姻中に取得されたものであれば原則として財産分与の対象となります。これらは夫婦が協力して形成した共有財産とみなされるため、その評価額や分与方法が重要な争点になります。
また、これらの事業用資産に対応する事業ローン等の負債も分与の対象に含まれます。そのため、実務上は資産と負債を一体として評価し、全体のバランスを踏まえて分与割合を決めることが多いです。
事業用であることを理由に資産が分与対象から除外されるわけではありませんが、経営の継続性や配偶者の寄与度などを考慮し、結果的に分与割合の調整が行われることがあります。
妻が経営や事務にどの程度関与していたか、また家計と事業資金を分けて管理していたかといった事情は、この分与割合の調整時の判断材料となりえます。
(4)医療法人を経営しているケースの財産分与
個人で開業している場合とは異なり、医療法人を設立していると、財産(病院、クリニック、不動産、医療機器など)は法人名義、すなわち法人の所有物とされ夫婦の財産とは関係ないものと扱われるのが原則です。
ただし、配偶者が医療法人に資金援助をしていた場合や経営面で協力をしていた場合は、その貢献度を考慮して分与対象とする余地があります。また、法人の代表である夫が法人の資産を自分のものと認識していたり、個人の財産と混在させて使用していると認められるような場合も同様に共同財産とされる余地があります。
法人と個人の財産を切り分け、夫婦の貢献度を評価するには、法的・会計的な両面からの分析が欠かせません。
(5)勤務医の財産分与
病院から給与を支払われている勤務医の場合は基本的に会社員の離婚のケースと同様に考えることが出来ますが、その給与の水準が高いことから、預貯金や投資資産、不動産の扱いが問題になりやすい傾向にあります。
また、特に大学病院や大規模病院勤務の場合は、退職金が大きな金額になることがあります。
退職金も夫婦の同居期間に対応する部分は共有財産として財産分与の対象となり、勤務医の妻が専業主婦であった場合も家事や育児に専念することで夫の収入獲得を支えていたと評価され、財産分与の割合は2分の1ルールが適用されるのが原則です。
もしまだ支払われていない退職金の財産分与について協議する際は、退職金見込額を証明する資料を収集するなど、具体的な裏付けが必要です。
婚姻費用・養育費について
離婚までの婚姻費用や離婚後の養育費については、夫婦双方の年収と子どもの人数・年齢から計算する、いわゆる「算定表」に従って決められることが多いということは良く知られているように思います。
ですが、この算定表の義務者(支払う側)の年収について2000万円までしか記載されていないことはご存知でしょうか。
医師は一般的に収入が高く、中には年収が2000万円を超えている方も多くみられます。このような高収入な相手との離婚にあたり義務者の年収をどのように考えるかについては、以下の2つの考え方があります。
A 義務者の収入は上限2000万円とすべき(打ち止めあり)という考え方
B 義務者の収入は実際の年収額をもとに計算すべき(打ち止めなし)という考え方
このうち、Bの考え方による方が、婚姻費用や養育費はより高く算定されることになるため、権利者(支払ってもらう側)としてはBの考え方に立って主張したいと考えられることでしょう。
この点については、最高裁判所も明確に見解を示していないため、それぞれの立場に有利な主張を行っていくことになります。調停で争っているときには、夫婦双方の今までの生活状況や貯蓄額、子どもの年齢や進学費用等の特別な支出の予定の有無など、裁判所は個別の事案ごとに具体的な事情を考慮するため、客観的な証拠を基に裁判官に納得してもらえるよう主張しなければなりません。
医療法人と配偶者との関係について
(1)配偶者から医療法人への出資
夫が医師である夫婦においては、夫だけでなく妻名義でも医療法人に出資をしていることが多くあります。
そのため、夫婦が離婚するにあたっては、妻名義の出資分を適切な時価で買い取ってもらうなど、財産分与においても考慮されなければなりません。夫婦間の問題と医療法人との間の問題は全く別もので、離婚したからといって医療法人への出資がきちんと処理されるわけではありませんので、この点を見過ごさないように留意しておきましょう。
(2)従業員として雇用されていた場合
類似した問題として、医師である夫に妻が従業員として雇用されていた場合は、離婚に伴い従業員の地位をどうするかという問題が生じることがあります。
基本的には「雇用関係を解消する」という選択をとられることが多いとは思いますが、原則として、解雇は、客観的・合理的な解雇理由があり、かつ社会通念上相当と認められない限り無効とされる(労働契約法第16条)ことは念頭に置いておきましょう。実務上は、金銭的な補償との引き換えに合意退職の形をとることが多いです。
医師・医者との離婚はお早めに弁護士に相談を
(1)離婚後の財産分与には期間制限がある
財産分与の請求は、離婚後は2年以内にしなければならないという法律上の制限があります。この期間は、消滅時効とは異なり支払督促などによっても更新されず、離婚から2年が経過すれば無条件で権利が消滅してしまうという強力な制限です。
財産分与は夫婦双方が正直に全財産を相手に開示することがその大前提としてありますが、夫が医師のケースでは夫名義の財産が高額で、種類も多いために婚姻期間中に妻がその全てを把握しきれていないことも多く、「自分の知らない財産がもっとあるのではないか」「相手の言う財産の評価額は妥当なものなのだろうか」と疑わしく感じられることもあるかと思います。
ですが、ご自身で相手の財産の調査・評価をするには難しいことも多く、時間がかかった結果、財産分与請求の期限が過ぎてしまうという危険があります。
(2)弁護士に相談するメリット
医師である夫との離婚では、夫名義の財産の価格をどう評価するか、財産分与の割合は2分の1とすべきかどうか、離婚後の養育費をどのように支払ってもらうか…といった点の協議内容次第で離婚後の生活が大きく変わってしまいます。そのため、相手も弁護士をつけて協議に臨んでくることが多いです。これに対し、こちらが弁護士をつけずに交渉していくことは非常に厳しいと言わざるを得ません。
少しでも有利な条件で離婚を成立させたいなら、ぜひ弁護士にご依頼ください。時間や手間のかかる財産調査も弁護士に任せることができますし、夫婦間で争いがある場合でも、離婚に関して経験を積んだ弁護士が対応するため、相手の要求に屈することなく協議を進めていくことができます。
弁護士法人リブラ共同法律事務所では、医師である配偶者との離婚についても多数の案件を取り扱ってきた実績がございます。医師との離婚にあたっては特に注意を要するケースが多いため、お悩みの方は、弁護士法人リブラ共同法律事務所へぜひご相談ください。
監修者

- 弁護士法人リブラ共同法律事務所は離婚事件を中心に取り扱い、東京・札幌を中心に全国の皆様から多数の相談、依頼をいただいております。離婚についてお悩みのことがございましたら当事務所までお問い合わせください。
最新の投稿
- 2026.02.12共同親権とは?
- 2026.01.12離婚時のマンション(不動産)の財産分与について弁護士が解説
- 2025.12.11看護師の離婚問題について弁護士が解説
- 2025.10.15アンダーローン不動産(持ち家)の財産分与の方法とは?不動産の財産分与に詳しい弁護士が解説
こちらもご覧ください
| ●弁護士紹介 | ●解決事例 | ●お客様の声 | ●弁護士費用 | ●5つの強み |