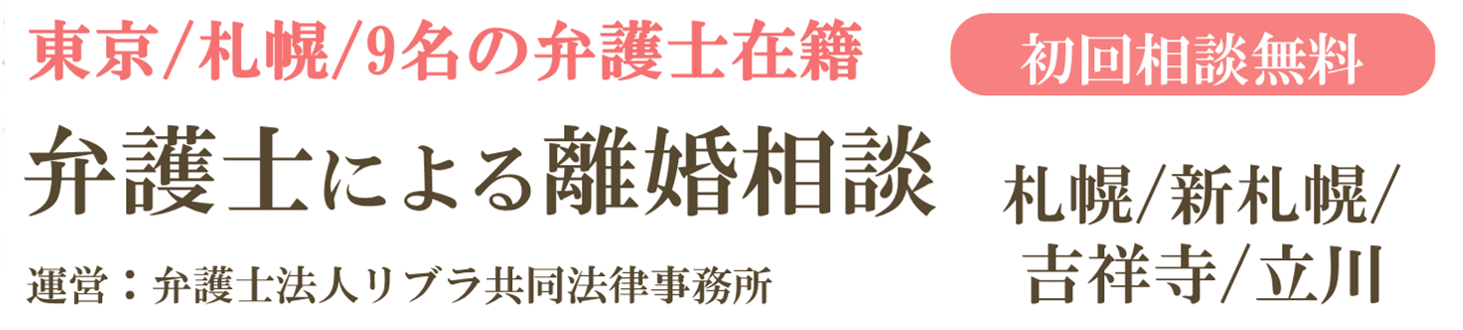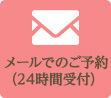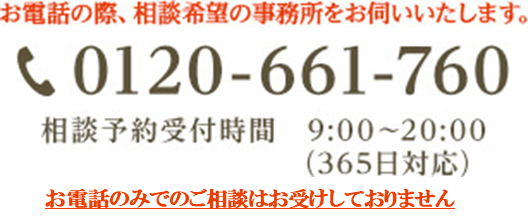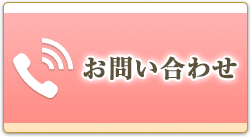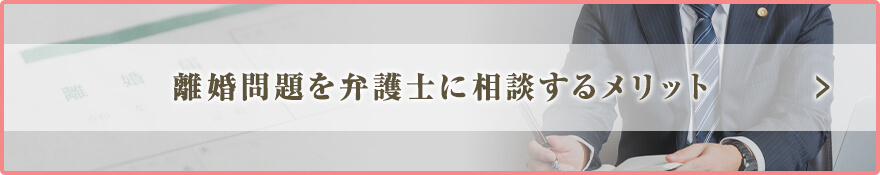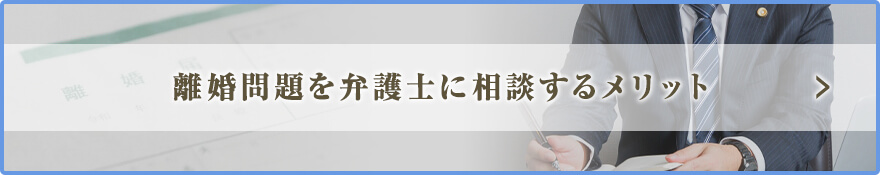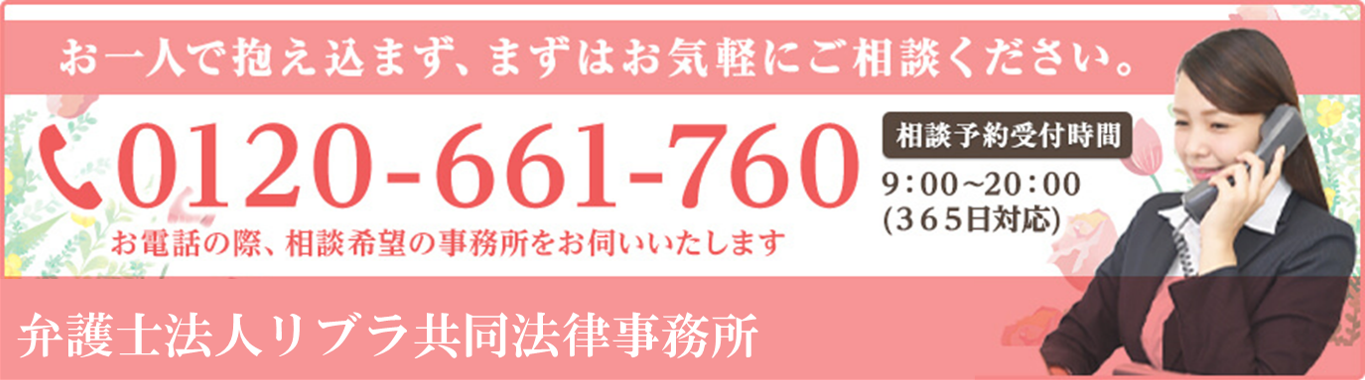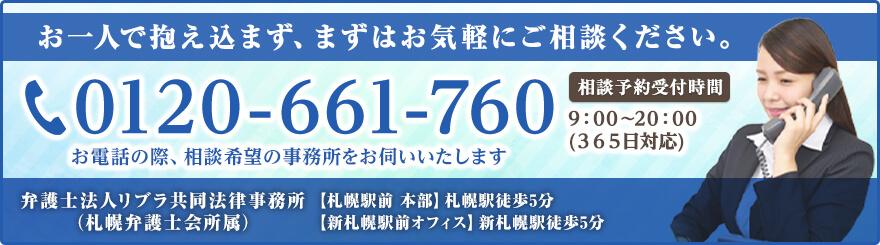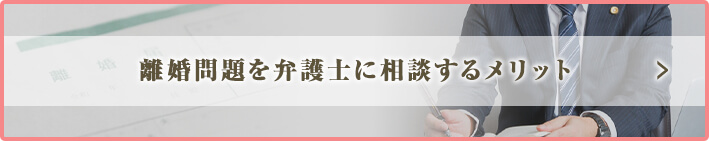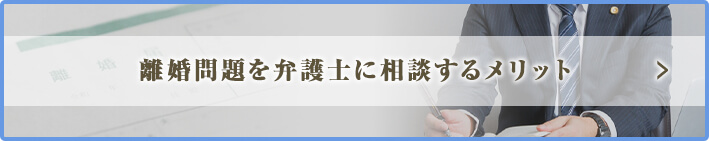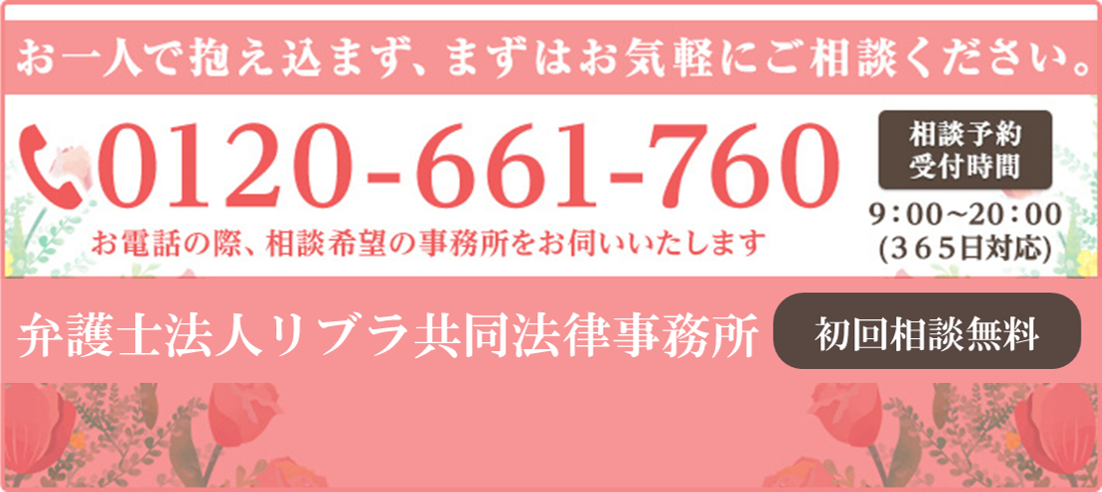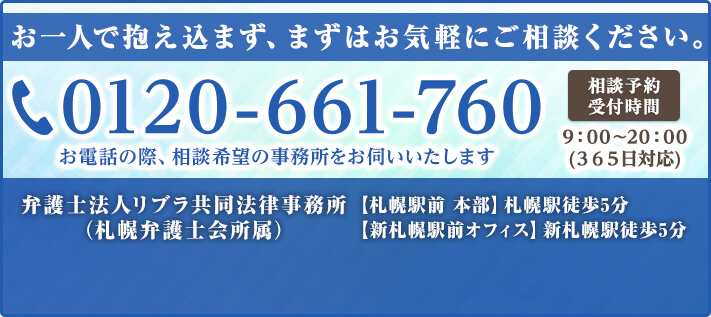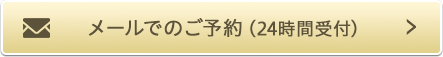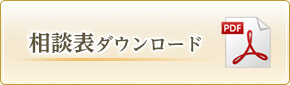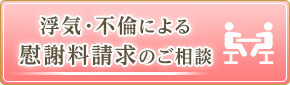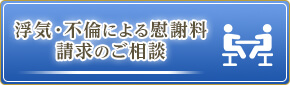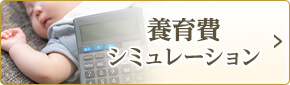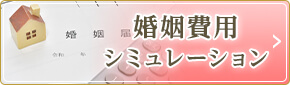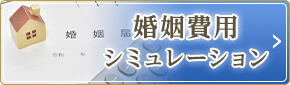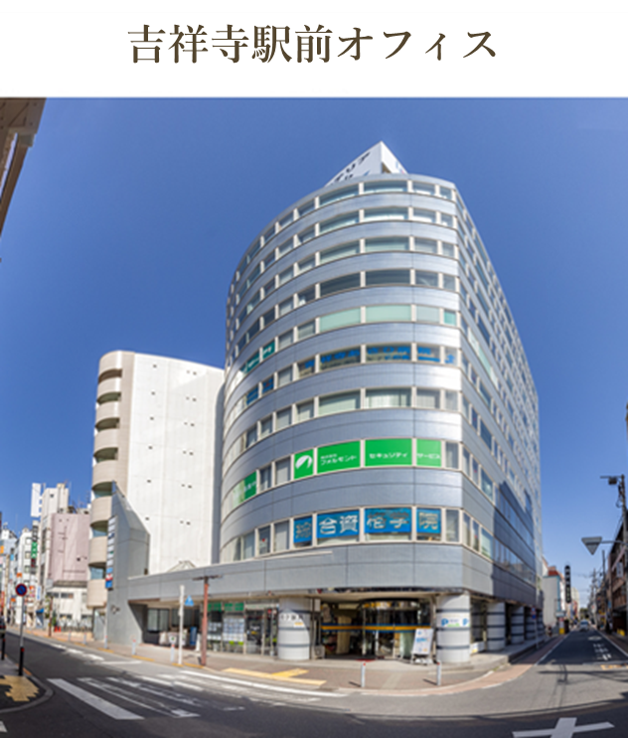熟年離婚における「退職金」の扱い
目次
熟年離婚で退職金の分与を求めることが可能か?
長年連れ添った夫婦が離婚する、いわゆる熟年離婚のケースでは、例えば定年が近い夫に対して専業主婦やパートで家庭を支えていた妻が「夫の退職金も分けて欲しい」とお考えになることが少なくありません。
婚姻期間が長くなるに伴い、退職金が財産分与の中でも大きな割合を占めていくことも多いため、その扱いが離婚協議において重要な争点になります。
財産分与(民法第768条)は「婚姻生活中に相互協力関係にあった夫婦の衡平を図る」という考え方に基づく制度であり、退職金についても夫婦が協力関係にあった期間、すなわち同居期間中に形成された部分については財産分与を求めることができるのが一般的です。ですが、まだ支給されていない退職金については結論が異なるケースもございます。
本記事では熟年離婚で退職金がどう扱われるかという点についてより詳しく、離婚問題に注力する弁護士法人リブラ共同法律事務所の弁護士が解説致します。
退職金の財産分与を求めることができるケース・できないケース
「財産分与を求めることが出来るか否か」、というのはすなわち、「その財産が夫婦の共有財産であるか否か」という問題になります。
原則、退職金の財産分与請求は可能
夫婦の片方が得た給与は「配偶者が家事や育児を通して相手を支えてきたために収入を得ることが出来た」という評価のもと、夫婦の「共有財産」に該当します。
そして、退職金も通常、勤続期間に応じて積み上げられるものであることから「給与の後払い」としての性質を有するため、それまで支払われてきた給与同様に共有財産に含まれるという取扱いが一般的になされています。
たとえ夫婦間に収入の差があったり、いずれかが専業主婦(専業主夫)だったりしても、その結論は変わりません。
「将来受け取る退職金」についての考え方
熟年離婚といっても、まだ退職はしておらず実際に退職金が手元にあるわけではないケースもあります。
ですがそのようなケースでも退職金が支給される蓋然性があれば支給予定額をもとに分与の対象とされることが一般的です。この蓋然性の判断には、職種や勤務先、別居時点までの勤続年数が考慮されることもあります。
例えば倒産の心配がない公務員の場合や、同様に倒産の可能性が低く退職金規定がしっかり整備・運用されている大企業に勤めている場合は退職金を財産分与の対象に含むという扱いがされやすく、勤続年数が長いほど、また年齢が高いほどそのまま定年まで勤め上げる可能性が高いとして定年退職時の退職金を基準とした財産分与が認められやすくなります。
なお、実際に財産分与として受け取る方法としては、将来の退職金分を現在手元にある他の財産で調整する方法や、合意書などで将来の分与を取り決めるといった方法などを検討することになります。
いずれにしても、受け取った(受け取る)退職金全額が夫婦の共有財産になるわけではなく、勤続期間のうち夫婦の同居期間が占める割合に応じた額のみが対象になる、という点には注意が必要です。
退職金の財産分与を求めることが出来ないケース
一方で、将来の退職金の支給が不確実な場合や、退職時期が未定で支給額も不明確な場合には、財産分与の対象とならないこともあります。
例えば、勤務先で退職金制度が定められていない、退職金支給の実績がない、といった場合は将来受け取れる保証がないとして分与の対象から除外されることがあります。
退職金の計算方法・調べ方
将来の退職金を財産分与の対象とする際は、その金額をどのように計算するかも問題になります。
退職金の計算方法
退職金の見込み額は「基本給×退職金支給率」によって計算されるのが一般的です。
この退職金支給率については会社ごとに定めた退職金規程に記載があり、勤続期間が長くなるほど高くなるほか、退職時の役職や自己都合退職か会社都合退職(定年退職を含む)かで異なる数値が定められていることが多いです。
実務では、定年前に自己都合退職により支給額が大きく変動する可能性が残っているようなケースでは、自己都合退職時の低い金額を基準に財産分与額が計算されることがあります。退職金規定の内容は人事部門などで確認することができ、就業規則の一部として記載されているか就業規則と独立して定められているかは会社によりけりです。
上述の式で求めた退職金見込額のうち、さらに分与対象となる金額がいくらになるかは、退職金見込額の総額に同居期間中の勤続年数が占める割合を掛けて算出します。たとえば、勤続30年のうち夫婦の同居期間が20年であれば、退職金全体の3分の2が分与の対象になります。
財産分与を求める側が配偶者の退職金見込額を調べるには
退職金を支給するかしないか、そして支給する場合の支給率に法律の決まりはなく、定め方やその内容は会社によって様々です。そのため、協議や調停、訴訟で将来の退職金について財産分与を求める際には、まずは配偶者本人からの情報提供を求めることになりますが、相手方が中々応じず話し合いが進まなくなるケースも多いです。
このようなケースでは、調停や訴訟の手続の中で家庭裁判所に調査嘱託を申し立て、家庭裁判所から配偶者の勤務先に対して、退職金見込額について回答を求めてもらうことがあります。
退職金を使われてしまうリスクに備えて
財産分与の基準時は別居開始時です。そのため、すでに退職金が支給されているケースでは、別居開始以降に配偶者がその退職金を使ってしまったことで、財産分与を求める権利があっても現実に分与できるだけの額が残っておらず回収が出来ない、という問題が生じる可能性があります。
このように配偶者に退職金を使われるリスクがある場合には、保全処分の手続を検討する必要があります。保全処分には大きく分けて裁判所が暫定的に義務者の財産を差し押さえる「仮差押え」と一定の行為を命じる「仮処分」がありますが、銀行口座に振り込まれた退職金の使い込みが問題になるケースでは、預金債権についての仮差押絵の命令を裁判所に申し立てることになります。
もっとも、これらの保全手続は強い効力を持つため、その必要性が認められるかどうかは厳しく判断されます。また、申立人は保全を要する財産の額に応じて一定額の担保金を裁判所に納める必要もあります。
熟年離婚で退職金に関する協議を弁護士に依頼するメリット
退職金を含む財産分与の協議では、制度の理解に加え、将来の支給額や対象となる金額の計算など、複雑な確認作業が必要になります。さらに、相手が協議に応じない場合には調停や訴訟などの法的手続きを取る必要が出てきます。
このような場面で、離婚問題に精通した弁護士に相談することで、法的に妥当かつ有利な条件での解決が期待できます。当事務所は、離婚協議・調停ともに多くの解決実績があり、累計4,000件以上(令和7年5月時点)の相談を受けてきた経験豊富な弁護士が、あなたの状況に応じて適切なサポートをいたします。
退職金の分与に不安や疑問を感じている方は、ぜひ一度ご相談ください。
監修者

- 弁護士法人リブラ共同法律事務所は離婚事件を中心に取り扱い、東京・札幌を中心に全国の皆様から多数の相談、依頼をいただいております。離婚についてお悩みのことがございましたら当事務所までお問い合わせください。
最新の投稿
- 2026.01.12離婚時のマンション(不動産)の財産分与について弁護士が解説
- 2025.12.11看護師の離婚問題について弁護士が解説
- 2025.10.15アンダーローン不動産(持ち家)の財産分与の方法とは?不動産の財産分与に詳しい弁護士が解説
- 2025.10.1570代女性の離婚問題
こちらもご覧ください
| ●弁護士紹介 | ●解決事例 | ●お客様の声 | ●弁護士費用 | ●5つの強み |