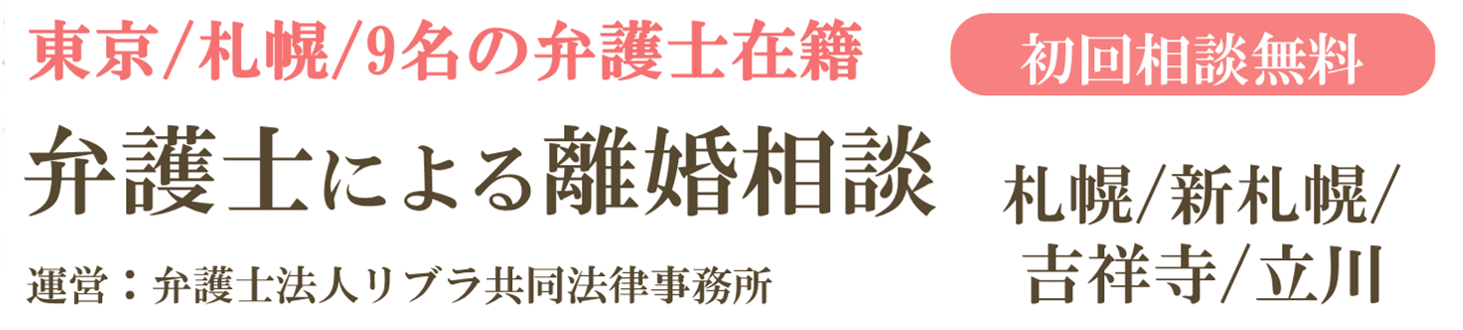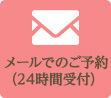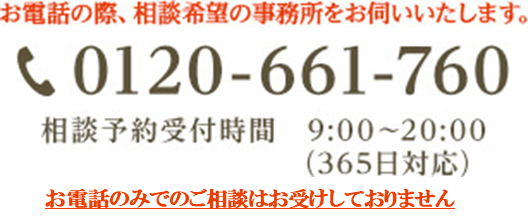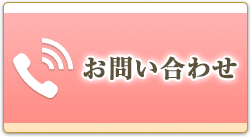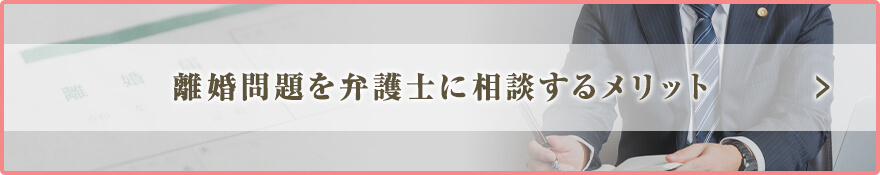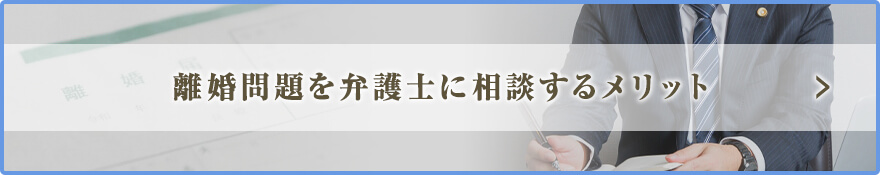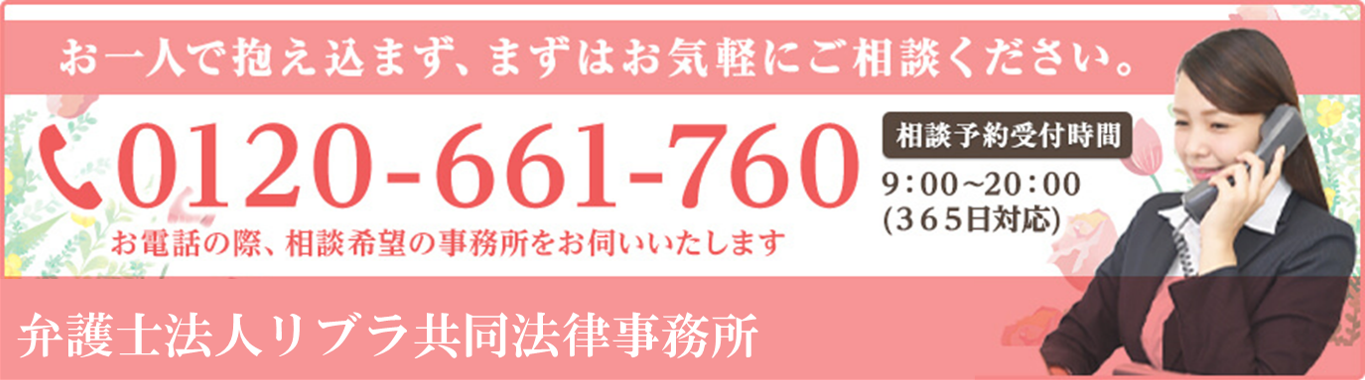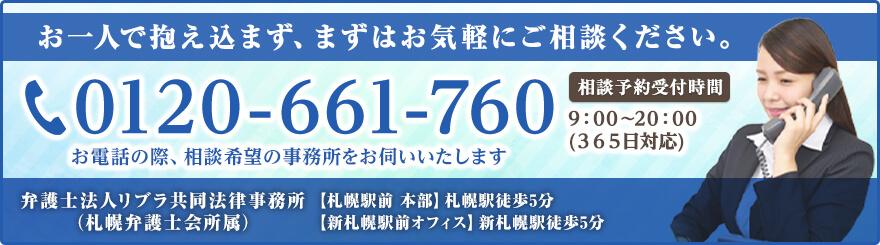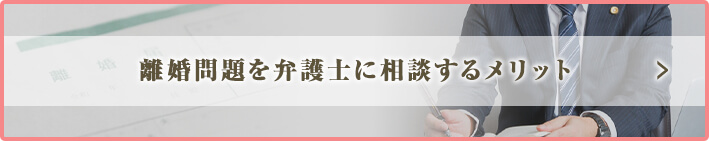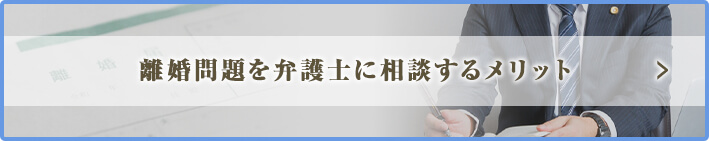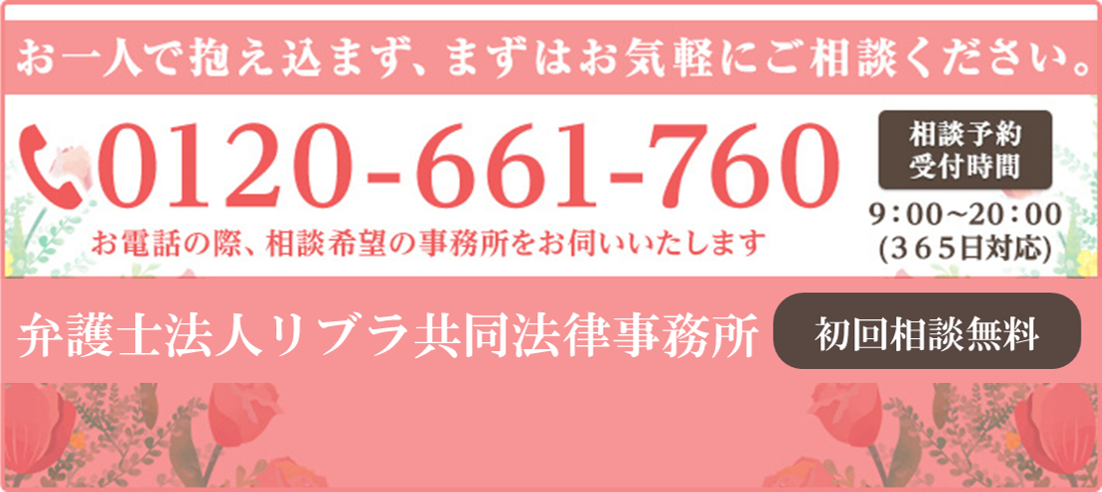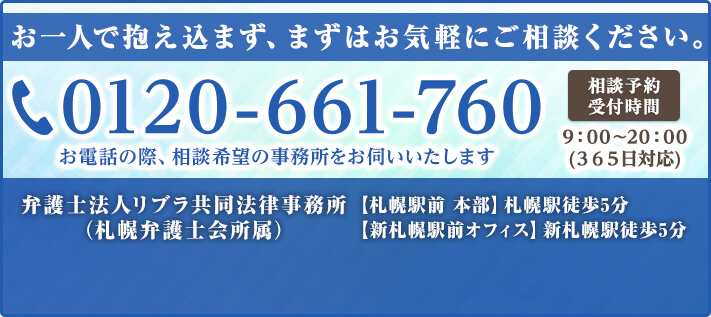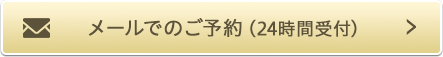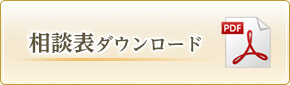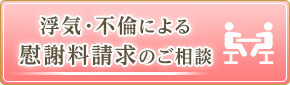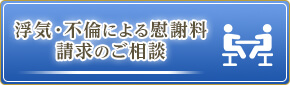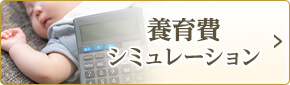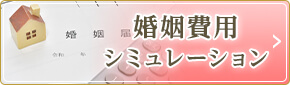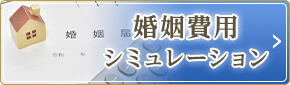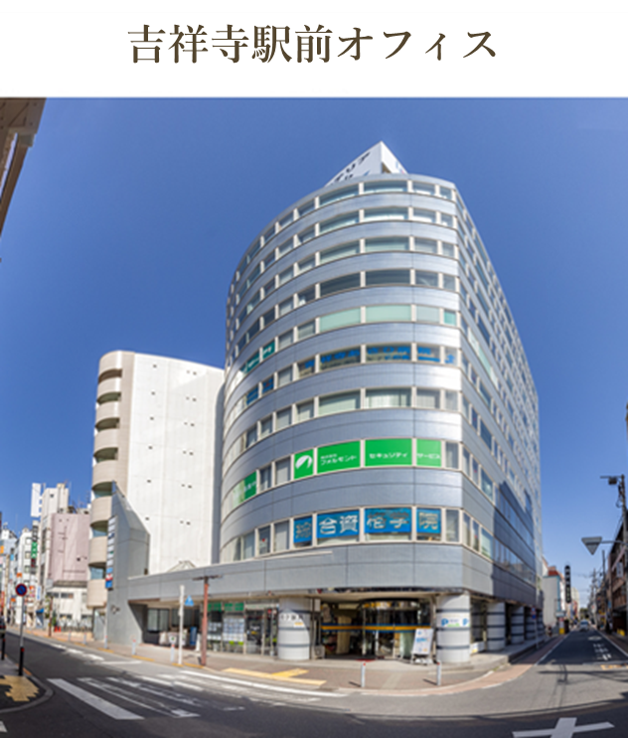年収2000万円を超える方の離婚問題|養育費・婚姻費用の算定
目次
離婚するご夫婦の収入が高いほど、またご夫婦の収入の差が大きいほど、金銭面の争いが複雑になりやすく、特に養育費や婚姻費用(別居中の生活費負担)の算定が大きな課題になります。
一般に家庭裁判所で運用される「養育費・婚姻費用算定表」では、支払義務者が給与所得者の場合は年収2000万円、自営業者の場合は1567万円が上限になっており、その範囲を超える収入を得ている方が支払う婚姻費用や養育費については個別に判断されています。
本記事では離婚問題に注力する弁護士法人リブラ共同法律事務所の弁護士が、このような算定表で想定されている収入のある方の離婚について、特に養育費・婚姻費用に焦点を当てて解説致します。
養育費・婚姻費用の一般的な算定の流れ
算定表を用いて簡易・迅速な計算が可能
実務でも、裁判所が公表している「養育費・婚姻費用算定表」を用いた計算をするケースは多いです。
この算定表は、養育費については子の人数・年齢、婚姻費用については子の有無・人数・年齢に応じて複数作成されており、どの表も縦軸には支払う側(義務者)、横軸には支払いを受ける側(権利者)の年収が記載されています。
ここでの「年収」は、原則として給与所得者であれば源泉徴収票の「支払金額」(控除前の金額)、自営業者であれば「課税される所得金額」を指します。それぞれの数値を用いて年収が交差する点を参照し養育費・婚姻費用月額の目安が分かるようになっています。
参考:裁判所|平成30年度司法研究(養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究)の報告について
なお、裁判所の算定表に書かれている養育費や婚姻費用の額は子どもの教育費も考慮して決められていますが、この教育費は子どもが公立学校に通うことを想定した範囲にとどまっています。
そのため私立学校への進学、習い事の費用などは「特別費用」として別途父母の分担について合意しておく必要があります。
算定表の基となる考え方(標準算定方式)に当てはめる方法
そもそも算定表に書かれている金額はどのように決められたのか、というところに立ち返ると、「標準算定方式」という計算方法があります。
標準算定方式によれば、養育費や婚姻費用の計算でまず行うのは①「基礎収入」の算定です。
この基礎収入とは、給与や賞与、事業所得などからから公租公課を控除したいわゆる可処分所得をいいます。
標準算定方式では、基礎収入の金額について、収入額に応じた一定の割合(基礎収入割合)を乗じて計算しています。
続いて、②子どもの年齢や人数に応じた「生活費指数」を確認し、子の生活費(養育費の場合)または権利者世帯の生活費(婚姻費用の場合)を算出します。
生活費指数とは、成人一人を100とした場合の子どもに振り分けられるべき生活費の割合のことです。
【養育費の場合:子の生活費を算出】
子の生活費
=義務者の基礎収入×子の生活費指数合計÷(100+子の生活費指数合計)
【婚姻費用の場合:権利者世帯の生活費を算出】
権利者世帯の生活費
=(義務者の基礎収入+権利者の基礎収入)×権利者世帯の生活費指数合計÷(義務者の生活費指数+権利者世帯の生活費指数合計)
そして、①②を踏まえて、③具体的な養育費・婚姻費用の算定を行います。
【養育費の場合】
支払義務者の年間分担額
=子の生活費×義務者の基礎収入÷(義務者の基礎収入+権利者の基礎収入)
【婚姻費用の場合】
支払義務者の年間分担額
=権利者世帯の生活費-権利者の基礎収入
この標準算定方式の考え方は算定表の上限を超える収入を得ているケースでも使うことになります。
年収2000万円を超える場合の修正
算定表の上限を超える場合の運用として、「上限をもって頭打ちとし、2000万円(自営業者の場合は1567万円)のゾーンで算定する」考え方もありますが、実務の多くは「上限にとらわれず個別事情に応じて調整する」見解に立ち解決を図ります。
もっとも算定表の上限にとらわれずに考えたとしても、基本的には標準算定方式に従い、基礎収入→子ども(権利者世帯)の生活費→義務者が負担すべき養育費(婚姻費用)額の順で計算をすることには変わりありません。
ですが、年収が2000万円を超えるケースでは、当事者個別の事情や、収入が上がるほど公租公課の比率が高くなったり貯蓄に回す割合が増えたりする傾向を考慮し基礎収入(可処分所得)額を低くする、といった調整が図られることがあります。このような調整が認められるには客観的資料に基づく事実認定を経る必要があり、専門家の分析のもと証拠を準備し、合理的な主張を組み立てることが出来るかどうかが鍵となります。
【基礎収入額の修正を主張する際の算定根拠とする資料の例】
・源泉徴収票
・確定申告書
・家計支出の明細
・預貯金通帳
・証券残高証明 など
婚姻費用や養育費を取り決める手順(協議、調停・審判)
まずは当事者間で協議して合意を目指しますが、意見が対立する場合は家庭裁判所に調停を申し立てます。
調停は調停委員が双方の事情を聴取して合意を図る場で、合意に至らないときは審判に移行します。
審判では双方が提出する証拠に基づき裁判所が判断を下すため、初期段階から書類や証拠を整理しておくことが重要です。合意が早ければ1~3か月、調停利用で数か月~半年程度要することもあります。早めの証拠収集が解決の近道です。
協議で取り決めた際は公正証書の作成を
高額の取り決めを口約束で行うのではリスクが高いため、公正証書による合意書作成を強く推奨します。
公正証書に執行認諾約款を付ければ、調停調書や判決書と同等の「債務名義」として扱われ、支払いが滞った際には直ちに強制執行を申し立てられるため、回収力が高まります。
婚姻費用・養育費算定が争点となるケースは弁護士にご相談を
年収2000万円を超える方の離婚問題は養育費や別居期間中の婚姻費用の算定表の上限問題のほかにも財産分与なども大きな争点となりがちで、個別の事案に応じた税務、資産評価、将来受給権の扱いなど多面的な判断が必要になります。
弁護士は基礎収入の算定、必要書類の収集、金融機関照会、税理士や鑑定人との連携、調停や訴訟での主張立証を担い、解決まで総合的なサポートが可能です。専門家と早めに方針を共有することで、不必要な争いを避けつつ、回収力の高い合意を目指すことが出来ます。
弁護士法人リブラ共同法律事務所は離婚協議・調停・訴訟において多数の解決実績がございます。初回無料相談で今後の見通しや必要書類の整理方法など、丁寧にご案内いたしますのでお気軽にご連絡ください。
監修者

- 弁護士法人リブラ共同法律事務所は離婚事件を中心に取り扱い、東京・札幌を中心に全国の皆様から多数の相談、依頼をいただいております。離婚についてお悩みのことがございましたら当事務所までお問い合わせください。
最新の投稿
- 2026.01.12離婚時のマンション(不動産)の財産分与について弁護士が解説
- 2025.12.11看護師の離婚問題について弁護士が解説
- 2025.10.15アンダーローン不動産(持ち家)の財産分与の方法とは?不動産の財産分与に詳しい弁護士が解説
- 2025.10.1570代女性の離婚問題
こちらもご覧ください
| ●弁護士紹介 | ●解決事例 | ●お客様の声 | ●弁護士費用 | ●5つの強み |