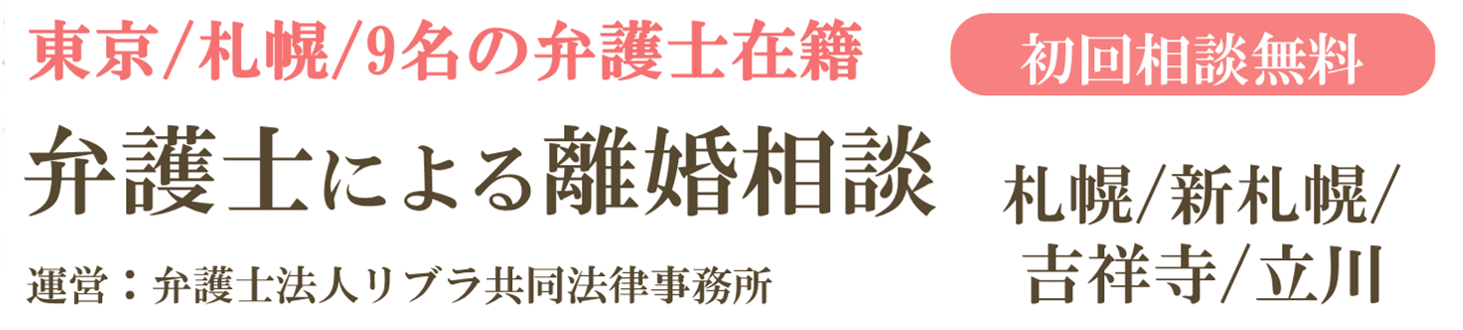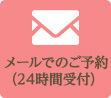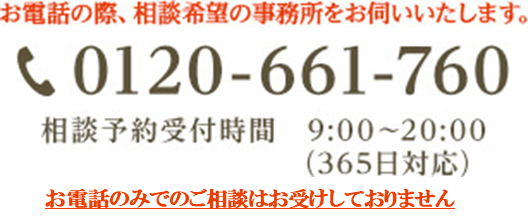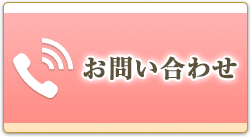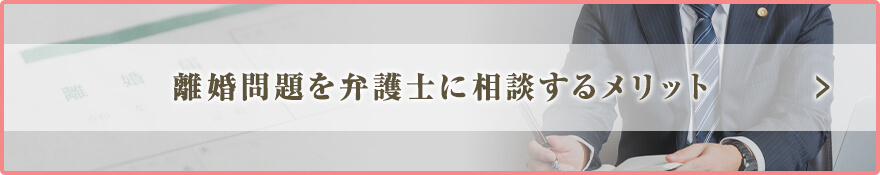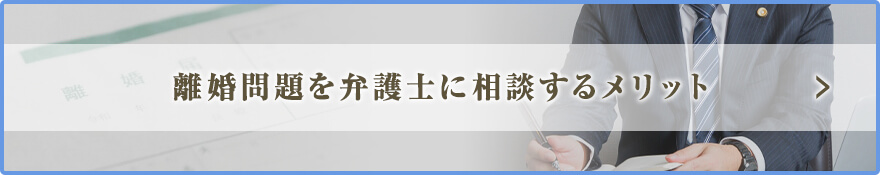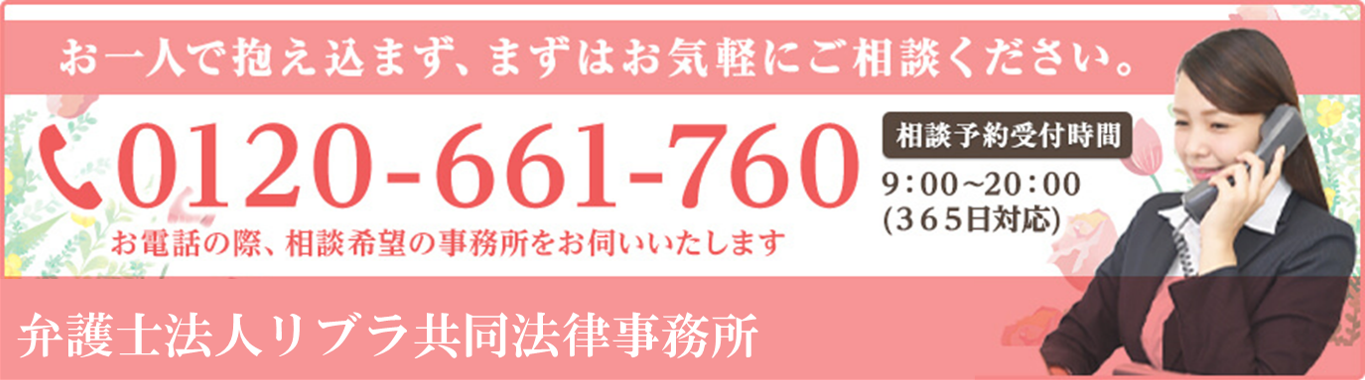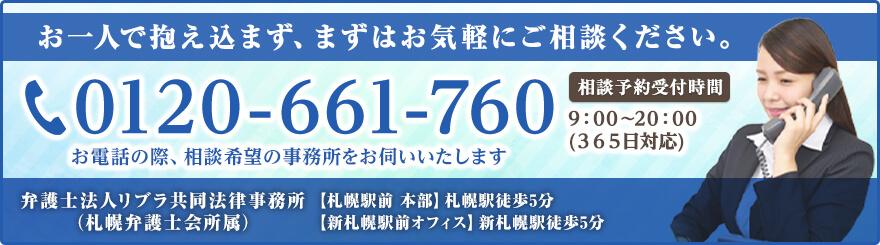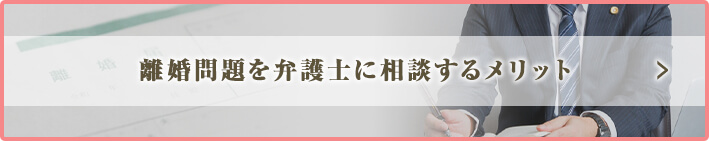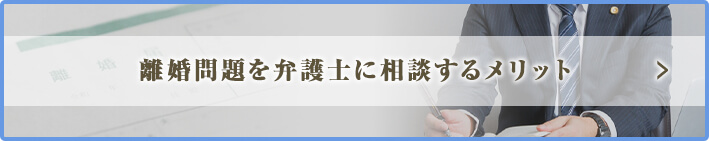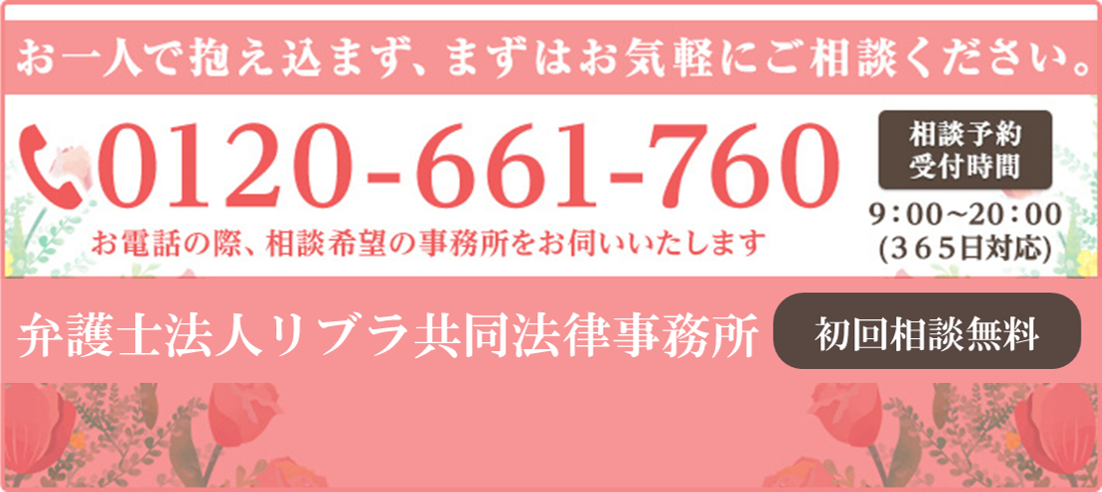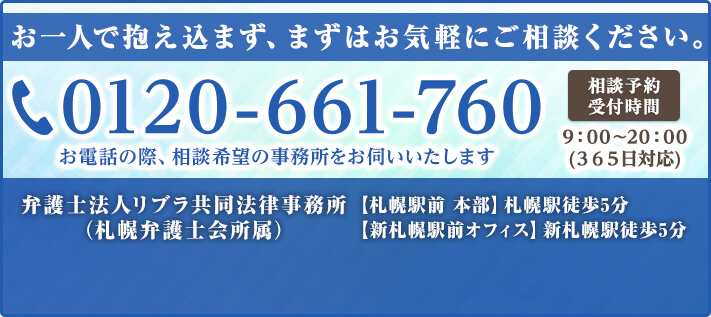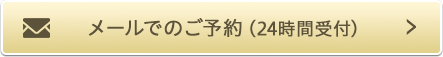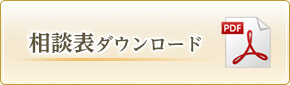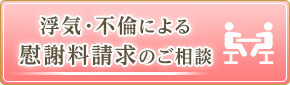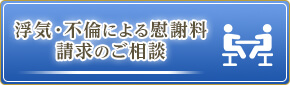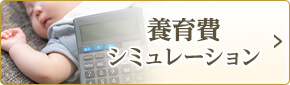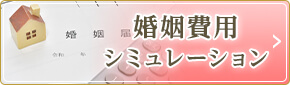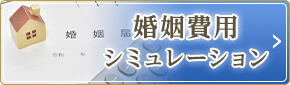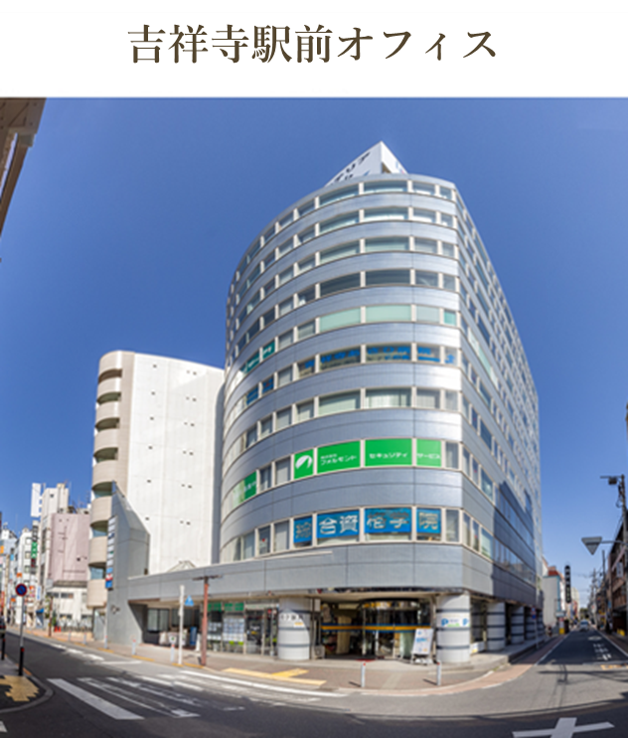不動産(持ち家)の財産分与
目次
不動産(持ち家)の財産分与
財産分与は,夫婦が婚姻中に築き上げた財産を清算する制度です。
この対象財産には,不動産も含まれますが,不動産はその評価額が大きいこと,住宅ローンを組んでいるケースが多いことから,財産分与においてはもっともシビアに争われる問題と言えます。
住宅ローンも財産分与の対象になる?
婚姻後に取得した不動産は,夫婦どちらの名義となっていても,プラスの財産として財産分与の対象となります。
そして,マイナスの財産である住宅ローンについても,夫婦どちらの名義であるかを問わず,財産分与に当たって考慮することとなります。
不動産(持ち家)の財産分与で考えること:「住み続ける」か「売却」か
持ち家の財産分与の方法としては,大きく分けると「住み続ける」または「売却する」かのいずれかになります。
ただし,どちらの方法をとるにしても,持ち家およびその住宅ローンが夫婦いずれかの単独名義なのか,それとも夫婦の共同名義になっているのか,によって具体的な手順が変わってくることになります。
持ち家の名義は登記簿など,ローンの名義は契約書や償還予定表などで確認しておきましょう。
夫婦いずれかの単独名義になっている不動産(持ち家)の財産分与
持ち家およびその住宅ローンが夫の単独名義になっているケースを例に考えてみます。
持ち家に「住み続ける」場合
まず,持ち家及び住宅ローンの名義人である夫が離婚後も住み続けるという方法があります。
この方法は夫が持ち家(プラスの財産)と住宅ローン(マイナスの財産)の分与を受ける形となり,離婚後も夫自身で引き続きローンを返済していくことになります。
妻側としては,住宅ローンの連帯保証人になってしまっていないか確認しておくことが大切です。
これに対して,名義人ではない妻や子どもが住み続けるという方法もあります。
この方法をとるときは,住宅ローンの名義人となっている夫がそのままローンの返済を続けることも併せて取り決められることも多いです。
もっともこの方法は「夫がローンの返済を怠ると家が差し押さえられてしまう」,「夫が勝手に自宅を売却してしまうかもしれない」といった妻側のリスクも伴います。
このようなリスクを回避するために,妻側はローンを負担する夫に代償金や解決金といった名目で一定の金銭を支払う(自宅を使用貸借状態とする),ローンの残額や妻自身の返済能力次第では名義人を妻に変更して住み続ける,といった対策が考えられます。
持ち家を「売却」する場合
夫婦のいずれも持ち家に住むことを希望していない場合には,持ち家は売却し,その売却益を夫婦で分割することになります。
持ち家がアンダーローン,すなわちその評価額がローンの残額を上回っている状態であれば,売却により得たお金でローンを完済し,売却にかかった経費を差し引いて残った利益を夫婦で分け合うことになります。
しかし,オーバーローン,すなわち評価額がローンの残額を下回っており,売却で得られたお金を全額返済に使ってもローンを完済できない状態であれば,残りの財産を充ててローンの残額を返す必要があります。
そうしたことから,オーバーローンの持ち家の売却にはローンを組んだ金融機関の同意が必要とされていますが,夫婦の現金や預貯金などで完済できる見込みがなければ金融機関の同意が得られず持ち家の売却という選択自体が出来ません。
夫婦の共同名義になっている不動産(持ち家)の財産分与
持ち家に「住み続ける」場合
持ち家などの不動産が共同の名義になっている場合,売却や担保の設定などは共有している全員の同意によって行う必要があります。
そのため,持ち家が夫婦の共同名義になっており,かつ離婚後はどちらかが住み続けることにするのであれば,後の不便を避けるために住み続ける側の単独名義に変更することが推奨されます。
また,持ち家が夫婦の共同名義になっているときには,その住宅ローンも夫婦共同で組むペアローンになっていないかどうかを確認しておく必要があります。
ローンが残っている持ち家のある夫婦が離婚する際,いずれかが返済を続けることを取り決めるケースは多いですが,ペアローンは夫婦が互いに連帯保証人となる契約であり,返済が滞ってしまうと元配偶者に支払義務が発生してしまうからです。
また,そもそもペアローンは夫婦双方が住宅に居住している実態があることが前提として組まれており,すでに家を出た人が債務を負っていること自体が契約内容に反してしまうおそれもあります。
そのため,もしペアローンを組んでいる持ち家に離婚後もいずれかが住み続けるのであれば,単独でのローンに一本化することが一般的です。
妻が住み続けるケースを例に考えてみると,夫の債務を妻が引き取る方法や,夫の代わりに妻の親族などの第三者を連帯保証人にする方法,妻が別の金融機関で単独名義のローンを組み,借り入れたお金でペアローンを完済する方法が考えられます。ただし,いずれの方法も金融機関の審査を経る必要があるので,審査が通らなければ持ち家の売却を検討せざるを得なくなります。
持ち家を「売却」する場合
すでに述べた通り,共有状態になっている不動産の売却には,名義人全員の同意が必要です。
そのため,持ち家が夫婦共同名義の場合は夫婦の合意のもとで売却しなければなりません。
この場合も持ち家が単独名義の場合と同じように,アンダーローンになっているかオーバーローンになっているかによって売却の方法が変わることになります。
住宅ローン付きの不動産の財産分与の手順
住宅ローン付きの不動産の財産分与は,基本的には以下の手順で検討を行うことになります。
① 不動産の現在価値を調べる。
② 住宅ローンの残債務額を確認する。
③ 不動産を取得するかどうか,住宅ローンの契約者を変更するかどうかを検討する。
④ 財産分与に関する交渉・調停・裁判
⑤ (必要に応じて)不動産の所有権移転登記,住宅ローンの契約者変更手続
以下では,これについて一つずつご説明します。
不動産の現在価値を調べる
不動産の現在価値を把握する方法としてもっともよく利用されるのは,不動産会社に無料の簡易査定をしてもらうことです。
また,場合によっては固定資産評価額(役所で取得できる固定資産評価証明書や,年に1回役所から送付されてくる固定資産税の決定通知書に記載されています)を参照することもあります。
不動産の査定額に争いがあり折り合いがつかない場合には,不動産鑑定士に鑑定を依頼することになりますが,費用がかかるためあまり行われることは多くありません。
住宅ローンの残債務額を確認する
住宅ローンの残債務額は,住宅ローン会社からもらう償還表を見れば把握することができます。
もしお手元にない場合には,住宅ローンの契約者から住宅ローン会社に問い合わせてもらえれば確認することが可能です。
不動産を取得するかどうか,住宅ローンの契約者を変更するかどうかを検討する
不動産の現在価値と住宅ローンの残債務額とを比べて,オーバーローンなのか(不動産の現在価値<住宅ローンの残債務額),アンダーローンなのか(不動産の現在価値>住宅ローンの残債務額)を確認します。
それを前提に,不動産を取得するかどうか,住宅ローンの契約者を変更するかどうかを検討することになります。
この点は特に,事案によっていろいろな事情を考慮した上で慎重に検討しなければなりませんので,弁護士に相談されることをおすすめします。
財産分与に関する交渉・調停・裁判
不動産を含めた夫婦の共有財産について,財産分与の方法を交渉・調停・裁判で決めることになります。
離婚調停の中で合わせて話し合いを進めることが一般的です。
(必要に応じて)不動産の所有権移転登記,住宅ローンの契約者変更手続
財産分与により不動産の所有権者を一方から他方に移す場合には,交渉・調停・裁判が終了した後に,移転登記手続が必要となります。
また,住宅ローンの契約者変更を行う場合には,財産分与の方法を決める前に,変更後の名義人の収入や資産状況について金融機関の審査を通過する必要があり,それを前提に,交渉・調停・裁判が終了した後,その金融機関において住宅ローンの契約者変更手続を行うことになります。
夫婦間で自由に住宅ローンの契約者を変更することができるわけではありませんので,ご注意ください。
不動産(持ち家)の財産分与でお悩みの方は弁護士法人リブラ共同法律事務所へご相談ください
離婚するとき,不動産(持ち家)の扱いが大きな争点となるケースは少なくありません。
どちらかが住み続けるのか,売却して代金を分けるのか,住宅ローンが残っている場合の負担をどう調整するのかなど,検討すべき点は多岐にわたります。特にローンが夫婦共有で組まれている場合など複雑な状況では,当事者だけで話し合うのは容易ではありません。
弁護士にご相談いただければ,ご夫婦間の協議はもちろん,不動産業者や金融機関との調整が必要になるケースでも,経験のある弁護士が関与することでスムーズな解決が可能になります。
さらに,調停や裁判となった際も専門的な主張立証を任せられるため,安心してご自身の離婚後の生活設計に集中することができます。
持ち家の財産分与は将来の生活に直結する重要な問題です。一人で悩まず,まずは弁護士法人リブラ共同法律事務所へお気軽にご相談ください。
監修者

- 弁護士法人リブラ共同法律事務所は離婚事件を中心に取り扱い、東京・札幌を中心に全国の皆様から多数の相談、依頼をいただいております。離婚についてお悩みのことがございましたら当事務所までお問い合わせください。
最新の投稿
- 2026.01.12離婚時のマンション(不動産)の財産分与について弁護士が解説
- 2025.12.11看護師の離婚問題について弁護士が解説
- 2025.10.15アンダーローン不動産(持ち家)の財産分与の方法とは?不動産の財産分与に詳しい弁護士が解説
- 2025.10.1570代女性の離婚問題
こちらもご覧ください
| ●弁護士紹介 | ●解決事例 | ●お客様の声 | ●弁護士費用 | ●5つの強み |